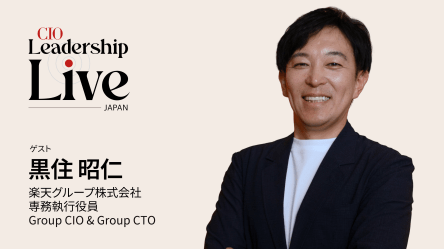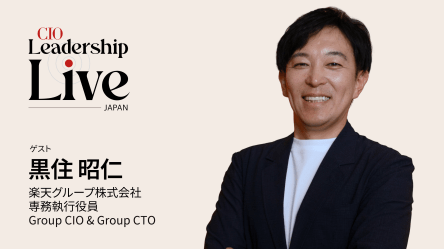日本企業でもマルチクラウドを取り入れる企業が増えています。マルチクラウドとは、単一のクラウド事業者に依存するのではなく、Amazon Web Services (AWS)、Microsoft Azure、Google Cloudといった複数の異なる事業者が提供するクラウドサービスを、目的や用途に応じて戦略的に組み合わせて利用するアプローチを指します。

かつて東日本大震災を契機として事業継続計画(BCP)の一環、すなわち災害対策という守りの文脈で語られることの多かったこの戦略は、今やコスト最適化とイノベーションの加速を両立させる攻めの経営基盤、競争優位の源泉へとその姿を変えつつあります。企業のクラウドサービス利用率は年々増加しており、2023年には7割を超えています(出典:総務省『令和5年通信利用動向調査』)。
最新の調査が示すように、日本のクラウド市場は2024年に前年比29.2%増と高成長が続き、2029年には約19.2兆円規模に達する見通しです(出典:IDC Japan「国内パブリッククラウドサービス市場予測」2025/02/20)。このダイナミズムの背景には、デジタル庁が推進するクラウドファースト政策と、IT人材の不足という深刻な課題への対応があります。本稿では、この日本型マルチクラウド戦略の進化の過程、その独自性、そして未来に向けた展望を多角的に分析していきます。
採用率の急上昇が示す経営戦略の根本的転換
近年の日本企業におけるマルチクラウド採用の勢いは目覚ましいものがあります。グローバルでは企業の76%がマルチクラウド戦略を採用しており(出典:HashiCorp『State of Cloud Strategy Survey 2023』)、日本でもこの動きは加速しています。特に、従業員1,000人以上の大企業に目を向ければ、その採用率は80%から85%に達しており、もはや世界水準に肩を並べていると言っても過言ではありません。この動きは、デジタル技術を経営の中核に据え、変化への対応力と競争力を高めようとする強い意志の表れです。
興味深いのは、日本企業が採用するクラウドサービスの具体的な構成です。近年のグローバル調査では、企業は平均して複数のクラウドサービスを併用していると報告されています(出典:Flexera『2024 State of the Cloud Report』2024/02)。日本においても、最も一般的な構成として2つから3つのクラウドを併用する企業が多く、これは一足飛びに全面移行するのではなく、慎重に効果を検証しながら段階的に導入を進めることを好む日本企業の堅実な特性を色濃く反映しています。
市場シェアにおいては、2021年度時点でAWSが43.8%、Microsoft Azureが31.5%、Google Cloudが13.2%となっています(出典:MM総研『企業のクラウド利用実態 2021年度版(IaaS/PaaS)』)。ここで見逃してはならないのが、国内プロバイダーも一定の存在感を保持している点です。これは、データの国内保管、いわゆるデータ主権に対する日本企業の高い意識と、国内ベンダーとの長年にわたる信頼関係を物語っています。
日本企業がマルチクラウド戦略を推進する上で、上位の動機として挙げられるのが「ベンダーロックインの回避」です(出典:HashiCorp『State of Cloud Strategy Survey 2023』)。この背景には、稟議など日本特有の合意形成プロセスが影響していると考えられます。特定の単一ベンダーに長期的に依存することは、将来の選択肢を狭め、組織の硬直化を招くリスクとして捉えられがちです。IBMは、ハイブリッドクラウド環境における接続の自動化によって、3年間で176%のROI(投資収益率)が期待できるという試算を公表しており、こうした経済合理性も経営層の判断を後押ししています。
また、2011年に発生した東日本大震災が、日本企業のクラウド戦略に与えた影響は計り知れません。地震や津波といった地理的リスクを常に前提としなければならない日本のビジネス環境において、事業継続計画は経営の根幹をなします。物理的に離れたデータセンターを持つ複数のクラウドプロバイダーを地理的に分散させて活用することは、もはや選択肢ではなく必須要件となったのです。
これに加えて、金融庁のFISCガイドラインや、厚生労働省・経済産業省・総務省が定める「3省2ガイドライン」など、業界ごとに定められた厳格な規制要件も、マルチクラウド採用を後押ししています。
深刻な人材不足と運用の複雑化という二重の課題
マルチクラウド戦略がもたらす恩恵は大きい一方で、その導入と運用には深刻な課題が伴います。中でも最も大きな壁として立ちはだかるのが、IT人材の不足です。2030年までに最大で79万人のIT人材が不足するという衝撃的な予測は、マルチクラウド管理の未来に暗い影を落とします。
実際に多くの企業が、スキル不足、コスト管理、セキュリティをマルチクラウドの主要な課題として挙げています(出典:Flexera『2024 State of the Cloud Report』)。AWSのような主要プラットフォームでは多数の新機能・サービスが継続的に投入されるため、技術者が継続的に学習し続けなければならない負担は増大する一方です。
政府もこの問題に本腰を入れており、デジタル人材育成のために「5年で1兆円規模」への拡大を目指す政策を掲げています。さらに、NTT東日本、ソフトバンク、IIJといった国内のマネージドサービスプロバイダーが、24時間365日体制でのマルチクラウド監視・管理サービスを提供することで、企業内の人材不足を補完し、複雑な運用を肩代わりする重要な役割を担っています。
業界別に異なる採用パターンが示す市場の成熟
マルチクラウドの浸透は、業界によってその様相を大きく異にします。金融業界では、FISCガイドラインなどから、セキュリティレベルの高いプライベートクラウドとパブリッククラウドを組み合わせたハイブリッド型の構成が主流です。
製造業は、Industry 4.0の流れを受け、平均を上回る高い採用率を示しています。IoTデータの統合分析にはAWS、基幹システムとの連携にはAzure、そしてAIや機械学習モデルの開発にはGoogle Cloudといったように、用途に応じて最適なクラウドを使い分ける戦略が定着しつつあります。
小売・ECセクターは、季節的な需要変動への対応やオムニチャネル戦略の重要性から、クラウド採用に極めて積極的です。セブン-イレブン・ジャパンがGoogle CloudのBigQueryを活用し、全国数千店舗の販売データをリアルタイムで分析している事例は、その代表例です。
一方、医療・製薬業界は、3省2ガイドラインという極めて厳格な要件が存在するため、慎重ながらも着実に導入を進めています。国内プロバイダーのサービスを優先しつつ、グローバルプロバイダーが提供するコンプライアンス認証を活用するという二面的な戦略が特徴的です。
ハイブリッドクラウドとの共存が示す現実的な移行パス
現在の日本市場を理解する上で重要なのは、ハイブリッドクラウドとマルチクラウドという二つのアプローチが共存しているという事実です。ハイブリッドクラウドは、パブリッククラウドと、自社で保有するプライベートクラウドやオンプレミスのインフラを、あたかも一つのシステムであるかのように緊密に「統合」して運用することを重視します。
対照的に、マルチクラウドは、複数のパブリッククラウドをそれぞれ独立したシステムとして運用し、業務の「目的別に使い分ける」ことを重視するアプローチです。この二つのアプローチの選択には、企業規模による傾向が見られます。セキュリティやガバナンスを最優先する大企業はハイブリッドクラウドを好み、俊敏性や柔軟性を求める中小企業はマルチクラウドを選択する傾向があります。
政府が掲げるクラウドファースト原則は、これら両方のアプローチを後押ししており、全国の地方自治体に対して、2025年度末までに基幹となる20の業務システムをクラウド上の標準準拠システムへ移行することを目指しています。このハイブリッドとマルチクラウドの共存という状況は、多くの日本企業が、長年運用してきたレガシーシステムと共存しながら現実的な移行戦略を描いていることの表れです。
日本のクラウド市場は、2030年に向けてさらなる成長が予測されています。この成長を牽引するドライバーとして、生成AIの本格的な活用、Society 5.0の実現、そして次世代通信規格とエッジコンピューティングの統合が挙げられます。
この巨大な市場機会を捉えるため、グローバルプロバイダーによる投資も加速しています。AWSは2027年までに2.26兆円を日本のデータセンターに投資することを発表しました。国内勢も動きを活発化させており、NTTデータとOracleが提携して提供するソブリンクラウドは、東日本リージョンで2025年12月、西日本リージョンで2027年3月にサービスを開始する予定です。
さらに未来を見据えれば、2028年から2030年にかけては量子コンピューティングとクラウドの統合が商用化フェーズに入り、カーボンニュートラルへの対応もクラウド選択における標準要件となるでしょう。
このような未来を見据え、日本企業が取るべき戦略は明確です。業界固有の規制要件を深く理解し、それを戦略の出発点とすること。国内プロバイダーやシステムインテグレーターとの戦略的な提携関係を構築すること。そして、何よりも重要なのは、これら全てを支える人材への継続的な投資です。日本のマルチクラウド市場は、災害対策という痛切な必要性からその歩みを始め、規制、文化、技術革新という要素が複雑に絡み合いながら、今や企業の競争優位性を左右するものとなっています。