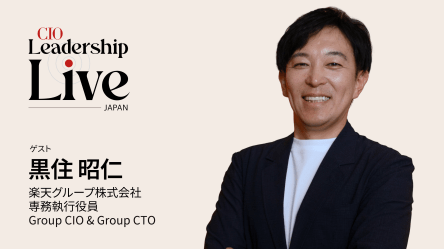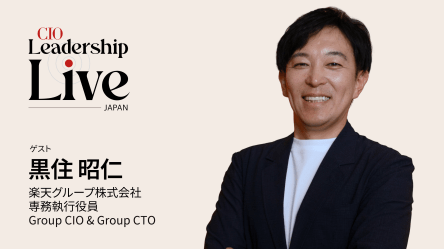生成AIの台頭で、米国の新卒採用市場に逆風が吹いている。「AIが若者の仕事を奪う」という現実は、日本にも訪れるのだろうか。実は、労働需給や産業構造、雇用慣行といった根深い違いから、日本が米国と同じ道をたどる可能性は低い。本記事では、なぜ両国で新卒採用の未来が異なるのか、その構造的な要因を多角的に解説する。

世界中で、生成AIがビジネスのあり方を根底から変えようとしています。特に米国では、その波が新卒採用市場に直撃し、エントリーレベルの業務がAIに代替され始めるという、これまでになかった現象が起きています。大学を卒業したばかりの若者たちが厳しい就職戦線に立たされているという現実は、日本でキャリアをスタートさせようとする人々にとっても、決して他人事とは思えないでしょう。しかし、結論から言えば、日本が短期的に米国と同じ道をたどる可能性は低いと考えられます。その背景には、労働市場の需給バランス、産業構造の特性、そして長年にわたり培われてきた雇用慣行という、両国間に横たわる根深い違いが存在するのです。
米国で深刻化する「新卒冷え込み」の実態
現在、米国では大学を卒業した22歳から27歳の若年層の失業率が5.8%に達し、国全体の失業率を上回るという憂慮すべき逆転現象が続いています。この背景には、IT大手を中心とした企業の採用抑制や、金利上昇、国際情勢の不安定化といった経済の不確実性があります。それに加え、生成AIがもたらした構造変化が決定的な要因となっています。これまで若手社員が担ってきたコーディングの補助、データ入力、市場調査の要約といった定型的なタスクが、AIによって急速に自動化されつつあるのです。その結果、企業は「エントリーレベル」の求人数そのものを絞り始めており、新卒者にとってキャリアの入口がかつてなく狭まっているという厳しい現実が、ニューヨーク連邦準備銀行の調査などによっても裏付けられています。
売り手市場が続く日本の「守られた」新卒採用
一方、日本の状況は米国とは実に対照的です。少子高齢化を背景とした構造的な人手不足は深刻で、2025年3月卒業予定者の就職率は98.0%と極めて高い水準を維持しています。有効求人倍率も1倍を超え、企業が人を求める「売り手市場」が続いています。特に、2026年卒業予定の大卒求人倍率は1.66倍に達し、中小企業を中心に採用意欲は依然として旺盛です。
この安定感は、日本の産業構造に起因する部分も大きいと言えます。米国の採用市場が巨大プラットフォーム企業の動向に大きく左右されるのに対し、日本のIT需要は、金融や製造業などで長年稼働してきた基幹システム(レガシーシステム)の運用・保守・段階的な刷新といった、人手を要する安定した領域に支えられています。経済産業省が「2025年の崖」として警鐘を鳴らすこのレガシーシステムの近代化は、一朝一夕にAIで自動化できるものではなく、要件定義から設計、テスト、移行まで、人の手による丁寧で緻密な工程が不可欠です。この巨大な需要が、若手技術者の育成の場を持続的に生み出す土壌となっているのです。
雇用慣行とAI導入の速度差がもたらす影響
さらに、日本独自の雇用慣行と法制度も、新卒市場の防波堤として機能しています。多くの日本企業が今なお基軸とする「新卒一括採用」と、配属後のOJTによる長期的な育成モデルは、社員をコストではなく「資産」と捉える思想に基づいています。一度採用の蛇口を閉めてしまうと、数年後の組織構成や技術継承に歪みが生じるため、短期的な景気の変動を理由に採用をゼロにするという判断には至りにくいのです。また、判例法理として確立された厳しい解雇要件も、米国のように短期間でエントリー層を大幅に削減するような、急激な雇用調整の強力なブレーキとして作用しています。
生成AIの導入ペースについても、日米間には明確な差が見られます。日本では、多くの企業がまず社内業務の効率化、例えば議事録の自動作成や文書の要約といった「補完的」な役割での活用からスモールスタートを切っています。個人の利用率も26.7%とまだ過渡期にあり、社会全体がAIとの協働を模索している段階です。新入社員の仕事を一気に「代替」するのではなく、AIをアシスタントとして使いこなしながら、より付加価値の高い業務を学ばせるという流れが主流であるため、採用の入口を急激に狭める要因にはなりにくいのが現状です。
日本が同じ道をたどらない理由とその先の課題
要するに、日本は「構造的な人手不足」「レガシーシステムの安定需要」「新卒を守る雇用慣行」という、米国にはない複数の強力な緩衝材を持っています。そのため、生成AIの台頭が直ちに米国の「新卒冷え込み」と同じ現象を引き起こすとは考えにくいのです。
しかし、これは決して楽観視できる状況ではありません。日本の真の課題は、この安定した入口を維持しつつ、いかにAIを「攻め」のツールとして積極的に活用し、国際競争力を高めていくかという点にあります。新入社員の仕事を奪うのではなく、AIを使いこなしながら若手を育て、より創造的で高度な課題解決に取り組める人材へと成長させていく。日本ならではの強みを活かした未来を設計することこそが、今後の重要な鍵となるでしょう。